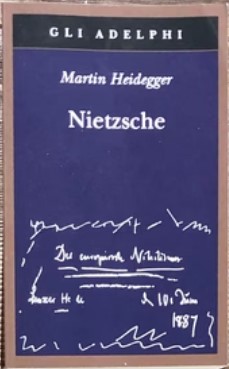20世紀形而上学批判序説 廣松渉からハイデガーへ 目次とリンク
第2章 現象学の根本問題
⑦
ハイデカーのニーチェ講義は1936 年から40年ぐらいまで行われた。ナチスとの蜜月期間が終わりどうもナチスにほされいた時期のようだが、だからといってハイデガーがナチスに加担していなかったわけではない。何よりも戦後もずっとナチス加担については沈黙を守り続けたようだ。

この時期『シェリング講義』や『形而上学入門』などの講義を精力的に行なっていたらしい。ハイデガー『ニーチェ』には四つの講義と一つの覚書が収録されている。今は平凡社ライブラリーで手軽に読めるようになった。そのニーチェ講義の中の「芸術としての力への意志」を扱いたいと思う。プラトン、アリストテレス以降のギリシャ哲学は存在を〈作られてあること〉としてとらえていたが、ソクラテス以前の思索家たちは存在を〈自ずから生成すること〉ととらえていた。ハイデガーは、ソクラテス以前の思索家たちの思想をどこからとらえてきたかというと、おそらくニーチェではないかと思われる。
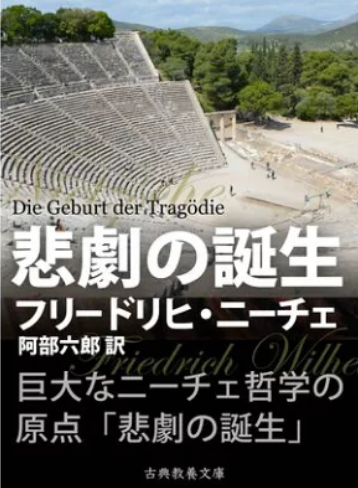
ニーチェは昔、文学的哲学者などとして扱われていた時期があったが、これは誤解で、もともと古典文献学という硬い学問をやって25才でバーゼル大学の助教授になった早熟の天才。ただ、最初の著書『悲劇の誕生』でソクラテスをこてんこてんのぼろぼろに言ったので当然クビ。後は年金で生計を立てながら著述家として活動をしていた。お父さんが牧師でキリスト教道徳に反発を小さい頃からしていた。このことはニーチェの哲学を考える上で重要。

ハイデガーが講義で扱っているニーチェの哲学的主著になるはずだった『権力への意志』もどうも編集した妹のエリザベートがいろいろ手を加えたようで、今ではマルクスの『ドイツイデオロギー』と同じ運命を辿った。それで白水社版のニーチェ全集では、『権力への意志』はもともとの草稿のまま載っている。ただ理想社の方の全集では妹が編集した『権力への意志』がそのまま残っているので、その相違は読もうと思えば読める。
『力への意志』は次の四つの巻からなっている。
第一書 ヨーロッパのニヒリズム
第二書 最高価値の批判
第三書 新たな価値定立の原理
第四書 訓育と育成
ニーチェは「ヨーロッパのニヒリズム」からヨーロッパ哲学の歴史をニヒリズムの歴史と捉える。それはプラトン以来のヨーロッパ哲学は、現実の外に、人間の現実から離れた精神のみに近づきうる超自然的、超感覚的な原理ープラトンの「イデア」、アリストテレスの「純粋形相」、キリスト教の説く「神」、ヘーゲルの「絶対精神」、マルクスの「価値実体」ーを設定して、それを通して自然や現実の人間の生活を理解しようとしてきた。
先日からトマス・アクイナスの『神学大全』(53巻全部読めるかわからないが)を図書館で読んでいるが、純粋形相、純粋理論に近づけば近づくほど良いとトマスは考えているような感じをもったが、純粋形相と聞けば聞こえはいいが、「無」の世界である。それを証明するかのように20世紀に入り二度の世界大戦を行い、その後もずっと戦争がいたるところで続いていることを考えるとニーチェの哲学的眼差しはあたっていると言えそうだ!
そして、第二書で「最高価値の批判」を行い、それまでのヨーロッパの形而上学・哲学に対して激しい批判を行い、第三書で、「新たな価値の定立」を示す。ハイデガーは、この「新たな価値定立」を土台にして「芸術としての力への意志」を講義した。
第三書でニーチェは、プラトン以来の哲学の価値観、存在概念を地上に叩きつけ生の回復を試みようとする。マルクスやフォイエルバッハがヘーゲル哲学との対決の中から唯物論に即して自然の復権を考えていたとするならば、ニーチェはプラトン批判をプラトン以前のギリシャの思索家たちの思想によってそれをなそうとしたと言える。
ニーチェがマックス・シュテイルナーを読んだかどうかはわからないが、かつてヘーゲル左派だったブルーノ・バウアーやシュトラウスとの交流はあったようだ。またフォイエルバッハのものは読んでいたと思われる。
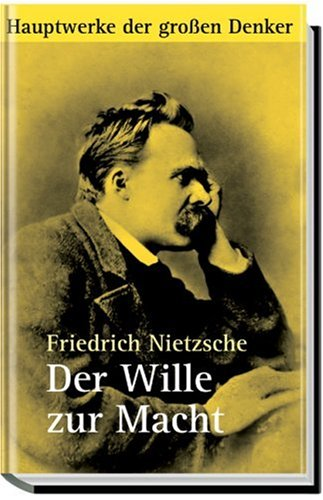
ハイデガーは、この講義の中でライプニッツ、シェリング、ヘーゲル、と言った教科書の哲学史では同じ枠組みで括れない哲学者の共通項を探す。それが「力への意志」Der Wille zur Macht のWille だと言うのだ。ヤコブ・ベーメもそんなことを書いていたが、意志、ドイツの哲学は主体の意志に引きつけて物事を考えるところに特徴があるということらしい。自然を数字に変えて自然をわかったつもりになっている実証科学とは違う。とにかく「力への意志」というのは生きる意志ということを言い換えたもののようである。そして、そこからは、ソクラテス以前の思索家たちの存在観、〈自ずから生成する〉ということに近づく。
⑧
ニーチェの哲学に
「プラトン主義のひとつの新しい解釈が示される。それは、ニヒリズムという事実の基本的経験から結果したものであり、プラトン主義のなかに、ニヒリズム、すなわち生の否定が現来する可能性への始原的かつ規制的な根拠を見るのである。
キリスト教はニーチェにとって〈大衆のためのプラトン主義〉以外の何ものでもなく、まさにプラトン主義である限りはニヒリズムにほかならない〜ニヒリズムへのニーチェの省察を視圏に含める時、プラトン主義の転倒は、ひとつの別の意味を持つ。
それは、ひとつの認識論的立脚点、つまり実証主義のそれとただ単純かつ機械的にとりかえることではない。プラトン主義の転倒とは、第一に、理想としての超感性的なものの優位に衝撃を加えることである」『ニーチェ」193頁
とハイデガーは、ニーチェ講義の中でニーチェ「力への意志」の核心がプラトン主義批判であることを描き出してみせる。
では、「ヨーロッパのニヒリズム」というプラトン主義批判の原理はどこに求められるべきか?超感性的世界には自然科学も含めてそれはありえない。ではどこか!素材ではない自然である。古代ギリシャ人は自然をピュシスと呼んだ。ニーチェ講義の中でハイデガーは、ピュシスについてこう語っている。
「さて、人間が彼を取り囲む存在者のただ中で、ひとつの立場を獲得し、自らの生活条件を整えようとする時、そして彼が存在者の克服にあれこれの手立てをめぐらす時、存在者に対する彼の方策は、存在者についてのひとつの知によって支えられ、導かれている。
この知がテクネーと呼ばれる〜テクネーはけっして製作や手工業的行為そのものではなく、常に知を意味し、生産を知的に導くという存在者の開示をさしている〜芸術家がテクニテースと呼ばれるのは、決して彼も手工職人であるがゆえではない。
芸術作品の産出が、実用品の産出と同じく、ピュシスのただ中で、そして、それに基づきつつ知的に方策をこらす人間の自己発揚だからである」
ピュシスについてはもう一度最終章で述べるとして、存在を〈作られてある〉とする存在観から〈自ずから生成する〉という存在観へ行きつくための方策はあるのか?
ハイデガーは述べる。
「プラトン主義の転倒ということが、プラトンの諸命題をいわばただ逆さにするだけの操作と同一視されてよいなら、単純な換置によって容易に答えられるであろう。たしかにニーチェ自身が事態をそのような具合に表現している。しかし、それは、大雑把な仕方でことを簡明にするがためではなく、彼自身がまたときには、なにか他のことを求めていながらそのような仕方で思惟しているところに起因している」
さて、ニーチェ自身は、「力への意志」を完成させることなく狂気のなかに倒れた。ハイデガーはニーチェについて、しかし、プラトン以来の形而上学をついに乗り越えられなかったとして次のように述べる。
「ニーチェが彼なりの仕方で、この永劫回帰の教説をもって思惟しているのはじつに隠されたまま、しかし、本来の主働因として全西欧哲学を支配している思想にほかならないのである。この思想を思惟しつつ、ニーチェは彼の形而上学をもって西欧哲学の始原に立ち返る」31
ここでハイデガーが言おうとしていることは、ソクラテス以前の思索家に深い理解を持ちながら、ニーチェは究極の存在概念に触れるとソクラテス以前の思索家のピュシスではなく、哲学の伝統的存在概念にたち戻ってしまうという点である。
ハイデガーは1930年代ニーチェ研究に没頭するが、しかし徐々に批判的になり、戦後さらなる「存在の問い」を、ピュシスへの問いを深めていくことになる。