20世紀形而上学批判序説 廣松渉からハイデガーへ 目次とリンク
第3章 ハイデガーのニーチェ講義

ハイデガーに「滞在」(ギリシャ紀行)(ハイデガー全集75巻)というもともと私家版として書かれたものだが1989年に「滞在」として刊行された著作がある。1962年、72歳のハイデガーが、妻とともにギリシャを訪れたが、この「滞在」という紀行文はその時の旅を綴った文章である。
「されど、かの王座やいずこに?神殿、はたまた玉杯の数々やいずこに?
不死なる美酒もて満たされたし、或いはまた神々を喜ばさんと捧げられれたるかの歌やいずこに?
いずこにそはそも輝くや、遠き方へと当たり行く震源の数多やいずこ?
デルフィーはまどろみ、いずこに鳴るやかの大いなる天命」
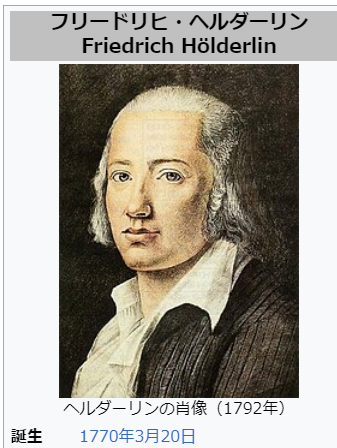
というヘルダーリンの「パンと葡萄酒」の第四連を冒頭に載せている。ハイデガーの最晩年の思索は若い頃から愛好したヘルダーリンの詩の解釈を通して行われることが多かったようだ!ギリシャを旅しながら、ギリシャに想いを馳せながら、ついにギリシャを訪れることのなかったヘルダーリンへの想いを綴っている。ヘルダーリンといえばヘーゲル、シェリングとは若き日友人であった。
古代ギリシャから2000年の時を経てアメリカの観光ホテルが立ち並び古代の面影をすっかりなくしてしまったギリシャを旅しながら
「ギリシャについて、しばしばかつ多様に、適切で知識に富んだ記述が充分なされていることは、あらためて言うに及ばない。われわれはだから、一緒に旅している船客たちが、デッキで憩いながら、しきりにそうした教化的な旅行案内や、洒落た筆致のギリシャに関する書物を読んでは勉強している様子にケチをつけるつもりはない。そのようなギリシャ旅行にはそれなりに正しい喜びがあるのであって、私は旅の間じゅう一度としてそれを非難するつもりにはなれなかった。だが、こんな考えも私の心を離れることは決してなかった。つまり、この旅が、ただわれわれ及びわれわれのギリシャ体験にのみに気する問題ではなくて、ーギリシャなる国自体に関わるものだーという考えである」
ハイデガーは、ギリシャを旅しながらかつてのギリシャの神々がいなくなり、もぬけのからになったギリシャを見てヨーロッパ文明そのものの行末を案じていたようだ!
「ギリシャの神々及びその最高の神は、もしいつか彼らが来たるとした場合、ただ形を変えて一個の世界を訪れるのみであろう。その世界の転覆するが、その根底を、古きギリシャの地の神々の国にもっているとはいえ。もしもかの地の思索家達が始まりゆく神々の逃亡に際して考えたこと、それが一個の成熟した言語において語れていなかったとするならば、もしもその語られたものが、そのあと異質の世界観の道具へと変形されていなかったとするならば、もしその語られたものが、そのあと異質の世界観の道具へと変形されていなかったとするならば、それならば現在、かの一切の遍く浸透している近代技術、またそれに帰属する科学および産業社会が持つ、その固有のものにおいてはなお覆蔵されている力というものが支配することはなかったであろう」
「もしも近代世界の横暴さが、神々のかつての逃亡に対して謎めいた関連にたっていないとするならば、その場合われわれ、即ち人間の単なる自己破壊とのみ語られている極度の危険において、なんらか救いとなるものを探し求めているわれわれが、逃げさった神々の不在を思うなぞといった、遠き方へと及ぶ回想を必要としていないであろうし、神々の変わり果てた姿での到来といった領域へと予見の想いをめぐらす必要もないであろう」

何もギリシャだけが、神々の消え去った世界ではない。ハイデガーにとって、西欧そのものが、神々が消え去った巨大な廃墟である。それゆえにニーチェは「神は死んだ!」と言った。否、ギリシャの神々でなくヨーロッパ中の神々が去って西欧の歴史が始まったというべきかもしれない。
ハイデガーはもともと保守派のカトリックで最初は神学を専攻している。しかし、アリストテレスを読むうちに、キリスト教世界に次第に疑問を募らせて遠くギリシャに想いを馳せるようになった。しかし、同じ「滞在」の中でこうも書いている。
「アジア的なものとの対決は、ギリシャ的生存にとって、一個の実り多き必然性であった。この対決は、われわれにとって今日、全く別の仕方で、遥かに大きな範囲で、ヨーロッパ並びに西欧世界と呼ばれるものの運命にくだされた決断というものである。
けれどもー全地球がー今や地球だけでは最早あるまいが、ー近代技術およびこれによって解き放たれた原子力作用圏という放射帯によって包み込まれており撃ち抜かれている限り、一夜にしてこの決断も、別の問いに姿をかえてしまっているというわけであろう。
即ち、果たして人間は今もなお、技術の本質が持つ強力な力をはらいのけることの出来る、なんらかの力への関係の中へと、自らを解放しうるのか否か、またその方策や如何に、という問いである。かかる世界情勢に直面して、ギリシャ精神の固有の回想は、浮世離れの道楽仕事に過ぎぬ。そう少なくとも思われるであろう」
読みにくい文章で恐縮だが、アジアとの闘いの中で生まれた、闘うために生まれた技術が20世紀の原子力時代になり、制御不能のものとなっている事態の中でヨーロッパの未来についてハイデガーは暗澹たる思いでいるようだ。この「滞在」というギリシャ紀行の中にハイデガーの晩年の思索がよく出ている。
「われわれにとって今日の世界と言われるものは、情報の技術的装置なるものの、見渡し得ざる錯乱であり、この錯乱は自らを、損なわれてはならぬピュシス(自然)の前に設置し、ピュシスの場所を占領してしまっている」
ローマ人はピュシスをnatura 自然と翻訳した。自然は生まれる、生まれてくる、それ自身から生まれ来たらしめるものである。
「自然」という名称は、しかし、違う意味でも使われる。人間と自然、歴史と自然、精神と自然というような使われ方である。この場合の使われ方は、自然を対象化して、自然を支配するための使われ方である。
しかし、自然ーギリシャ人がピュシスと読んでいた自然は、それ自身で生まれるものという意味であった。ハイデガーは、これを存在と呼ぶ。が、ハイデガーが古代ギリシャ哲学でそれ以上の思索を深めなかったことは、ハイデガーの最大の弱点でもある。
ギリシャ哲学の端初であるイオニア哲学のタレスは、今で言う小アジア、トルコにあたる。タレスはアジア系地中海民族の一つのフェニキア人の系統に属している。となるとギリシャ哲学もその出自は非ヨーロッパ地域ということになる。

ヨーロッパ地域外に哲学という天上のものをあつかう学問はなかった。それ以外の文化は自然物を自然物として隣人として扱い、原理にしなかった。アリストテレスの「形而上学」もメタフュジカー「自然学の後」でという意味らしい。空間と時間を超えた世界などあるのだろうか?
